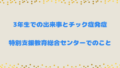小学1年生の初めての授業参観で我が子の発達を疑い始めました。調べてみると発達障害という言葉が出てきて当てはまる事ばかりで、色々考えた結果検査を受ける事にしました。

イルカくんの発達クリニックは、地域では有名なクリニックなので、月に1度ある初診予約日の電話予約の日は全然つながらず、予約が取れたのが初めて電話をかけた月から8ヶ月後の事でした。2月に電話がつながり、名前、住所、他にいくつか質問された事に答えたと思います。初診日は2か月後の4月の終わりに近い日でした。現在は半年待ちのクリニックなどもあるようです。
クリニックにもよりますが、イルカくんの病院は利用案内と問診票が送られてきたので、問診票に記入し、問診票、母子手帳、保険証、医療証を持っていきました。イルカくんと一緒に行き、イルカくんは別の部屋へ連れていかれ、私はイルカくんが生まれた時からの話しや、イルカくんの現状、今の悩みなどをお話ししたと思います。イルカくんは別の部屋で「お母さんをここで待っていようね」というていで、行動観察をされていたようです。イルカくんの現状を話している時に、「別の部屋で行動を観察させてもらっています。」と伝えられました。私は50分以上会話をしたと思います。その日は話しをしただけで終わりました。
2回目もイルカくんは検査のため別の部屋へ。私は、チェックリストのような用紙に沢山の質問?が載っていて、その質問に「よくある」「時々ある」「どちらでもない」「あまりない」「全くない」のような5段階評価から選んで丸を付けて答えていきました。10ページくらい、50問近くあったような記憶です。とにかくいっぱい答えた気がします。それでもイルカくんの検査の方が時間がかかり、待った記憶があります。
3回目もイルカくんと私は別々の部屋に分かれました。イルカくんはまた検査です。私は心理士の方と少しお話しをして、あとはイルカくんが終わるのを待ちました。イルカくんの検査は前回と同じように1時間ちょっとくらいかかりました。2つ日間に分けてWISC-ⅣとKABC-Ⅱと視覚優位、聴覚優位を調べる検査をしました。
4回目は私だけが行き、診断結果がでました。注意欠如多動症と自閉スペクトラム症と診断され、3枚のリストをもらい、WISC-ⅣとKABC-Ⅱと視覚優位、聴覚優位の説明を1枚ずつ丁寧にしていただきました。本当に腑に落ちる事ばかりで、検査の結果が間違いないと確信できるものでした。また、どう育てたら良いのか分からなくなっていたのですが、育て方の方向性が見えてきて、気持ちがとても軽くなりました。
息子が視覚優位なのか聴覚優位なのかを知ることができた事が、とても参考になりました。
視覚優位、聴覚優位とは
視覚優位も聴覚優位も、脳が「どのように入ってきた情報を処理するのが得意なのか」という特性です。これは「認知特性」と呼ばれ、誰にでもあるとされています。
視覚優位
【視覚優位】とは、耳から入ってくる情報よりも、目から入ってくる情報の方が処理をしやすい脳の特性のことです。
聴覚優位
【聴覚優位】とは、目から入ってくる情報よりも耳から入ってくる情報の方が処理をしやすい特性のことです
イルカくんは【聴覚優位】の子で、耳から入ってくる情報の方が処理をしやすい特性があります。そういうタイプの子は、漢字の読みを機械的に覚えたり、書き取りをする際に「見て、覚えて書く」ということが難しい場合があるのですが、イルカくんはまさにその通りで、漢字は読めるけど書けない。漢字を覚える事にとても時間がかかります。国語だけ異常にできません。ですので特に漢字の練習には工夫が必要です。
ネット情報ですが、『【聴覚優位】の子は、例えば「走」という漢字であれば、「土」「ト」「人」という、すでに知っている3つの文字に分けて、「ツチ、ト、ヒト」と唱えながら書いていくことで覚えやすくなります。』と書いてあったので、その通りに教えるようにしたら本当に覚えが早くなりました。我が家では、総はイトにハム心、許すはごんべんに午前の午、など、会話をしながら勉強します。ゴロ合わせのような響きの良いもの、言いやすさも大事かなと思います。もくもくと書いて覚えるよりも覚えるのが早いです。イルカくんは、書いた記憶よりもその漢字について話したことの方が覚えてるからだと思います。また、思うと想うの違いも、読んで理解するよりも、口頭で説明した方が頭に入りやすいようです。このように視覚優位、聴覚優位を知っている事で取り組み方も変わります。ですが、このやり方には難点が一つあり、漢字の勉強は私がいないと本当に覚えられないので困っていました。5年生になってからやっとほぼ一人でやってくれるようになりましたが、難しい漢字はいまだに『会話して覚えて定着させる』を続けています。
視覚優位・聴覚優位を詳しく知れるサイトがありましたので、載せておきます。
WISC-ⅣとKABC-Ⅱとは
WISC-Ⅳ
WISC-Ⅳは、子どもの困りごとの原因と対策を明らかにするためのものという役割だそうです。全体的な知的能力や記憶・処理に関する能力を測るテストとして国際的にもその信頼性が高く評価されています
WISCの結果は、子どもを理解するために活用されることになります。お子さんの生活の場である学校などが、子どもの特性を正しく理解することで、子どもが困っていることに、必要かつ的確なサポートを考えていくことができます。学童や塾、習い事などの場においても、必要に応じて必要な部分を伝えることにより、子ども同士のトラブルを防いだり、子どもに分かりやすい対応をしてもらえたり、子どもに合った学習法を取り入れてもらえたりします。
KABC-Ⅱ
KABC-Ⅱは知能検査の1つでWISC-Ⅳと並ぶ代表的な検査ツールです。
知能検査では唯一、基礎学力を計る学習習得度の評価も取り入れており、学習支援を目的として【認知尺度(認知処理力)】と【学習尺度(基礎学力)】を測定します。
100を基準に上下のばらつきをみることで発達水準を推定します。
【認知尺度】では得意な情報処理の仕方や計画性、理解定着力があるかが分かります。
【学習尺度】は何年生レベルの学力を持っているかが分かります。
簡単に説明すると、お子様の得意・不得意が分かり、学習の取り組み方が分かります。
WISC-ⅣとKABC-Ⅱの詳しくわかりやすく説明しているサイトがありましたので、載せておきます。

また、通信教材すららでは、発達障害関係なく、KABC-Ⅱの検査サービスのお申込をおこなっています。勉強が苦手なお子様向けに知能検査、科学的な根拠に基づく検査でお子様の得意・不得意を数値化し、学習支援法を提供しています。

特別支援学級などの教育の場でも使われている通信教材でもあります。