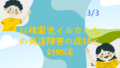発達障害の子やグレーゾーンの子にとって、療育施設や幼稚園選びはとても重要です。お子様に合っていない場所での生活は自尊心を傷つけられたり、自分に自信が持てず症状が悪化したり、ますますコミュニケーションが取れない子になってしまいます。それがトラウマとなり、成長に悪影響が出る場合もあります。また、家庭以外でのトレーニングが必要なお子様もいるかと思います。発達障害、グレーゾーンの子にとって、療育(発達支援)や周りの理解と協力は必要不可欠です。療育施設、理解のある幼稚園、先生と園児の関係性、お子様に合った場所かどうかの見極めが大事になってくると思います。誰かに””ここが良い”と聞いたから来てみたが、自分の子には合わなかったという事が良くあります。そこで、療育施設や幼稚園選びに必要な情報をわかりやすくまとめてみました。療育施設や幼稚園選びの参考になれば幸いです。
(※この記事を読むのに必要な時間は約20分ほどです。お時間のある時にじっくりお読みください。)

療育の対象となる子
療育手帳の有無は問われず、児童相談所や市区町村保健センター、医師によって療育の必要性が認められた場合は対象となります。そのため、手帳を持っていないからといって療育を受けられないというわけではありません。自治体から発行される【通所受給者証】の交付を受けることで支援を受けることができます。
【通所受給者証】があると、国と自治体から施設利用料の9割が支援されます。また、児童が属する世帯の市区町村民税額によって負担上限額が決まっており、利用月の1割負担額と負担上限月額を比較して安いほうが負担料金となります。この負担上限額は、【通所受給者証】に記載されます。生活保護や低所得の場合、負担額0円だったりしますので、負担上限額の詳しいお話しは市区町村の窓口でご確認ください。(利用施設によっては、別途おやつ代などの実費負担が発生することがあります)
通所受給者証とは
【通所受給者証】とは、児童福祉法による障害児を対象としたサービスを利用するための証書のことです。
【通所受給者証】は、障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていなかったとしても取得することができ、公的機関や民間の教室・事業所の利用が可能になります。
【通所受給者証】の取得方法は、まずはお住いの市区町村の窓口や発達支援センター、通われている発達クリニックなどに相談・確認をしましょう。グレーゾーンのお子様も、まずはお住いの市区町村の窓口で相談してください。(その後自治体の保健センターなどで、支援を受けたい旨を話し、手続きの手順を確認することになるかと思います。)もしくは、民間の施設で【通所受給者証】の取得サポートをおこなっている所もあります。後ほどご紹介いたします。
そもそも療育(発達支援)とは?
療育とは「教育」と「医療」を併せた言葉で、元々は身体障害のある子どもを対象に使われ始めました。療育は障害のある子どもへ治療をおこなうだけでなく、自立へ向けたさまざまな訓練をおこなうことも含んだ言葉です。その後身体障害のある子どもだけでなく、知的障害や発達障害などほかの障害のある子どもにも使われていきました。療育は基本的に障害や障害の可能性のある、18歳未満の子どもを対象としたサポートのことで、療育とともに「発達支援」という言葉もよく使われています。
療育(発達支援)施設とは
療育施設とは、簡単にまとめますと障害のある子ども及び発達が気になるお子さま一人ひとりに合った治療・教育を提供している場所のことを総称して使われる言葉です。
療育施設には「通所型」と「入所型」があり、その中でそれぞれ「福祉型」と「医療型」に分かれています。

通所型の福祉型には、『児童発達支援』、『放課後等デイサービス』、『保育所等訪問支援』の3つの支援があります。下記の【療育(発達支援)支援内容】で詳しく説明いたします。
通所型の医療型には、医療型児童発達支援があり、身体に障害のある未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、理学療法などの機能訓練を行います。
また、療育施設は『公的機関』と『民間の教室・事業所』があります。厚生労働省のガイドラインにより基準が決められており、その基準に沿ってそれぞれの施設(教室・事業所含む)が支援を実施しています。施設ごとに提供しているサービスが異なり、3つの支援を提供している施設や、1つだけ提供している施設など様々です。
公的機関 (公的施設)
公的な施設とは、自治体が管轄している『療育センター』、『発達支援センター』、『療育園』などの通園施設です。療育園には送迎バスがあったりします。センターや療育園の違いは、自治体によって内容にはかなりバラつきがあります。お住いの市区町村の窓口で詳しい話しを聞く事が、一番正確で最新の情報だと思います。
民間の教室・事業所(民間施設)
民間の法人などが運営している療育施設です。それぞれ対象や提供するサービスが異なっていて、親参加型教室などもあります。【通所受給者証】を必要とする施設は、公的な施設同様、【通所受給者証】に記載された負担上限額で利用できます。毎回先生が代わる所や、固定の先生がついてくれる所など様々です。民間の教室・事業所は、基本的にはご自身で調べる必要があります。お住いの地域によっては施設が少ない場合もあります。
尚、お住いの市区町村の窓口(福祉課)や通われている発達クリニックなどで民間施設の情報提供してくれる所もあるようですので、確認してみてください。
民間の施設でコペルプラススクールという所あります。現在38都道府県合わせて511教室あるとても大きな民間教室です。こちらでは【通所受給者証】の取得サポートも行っています。また、この教室には『相談支援事業所』があり、18歳未満の発達が気になるお子様や、そのご家族の生活・福祉に関するさまざまなご相談を無料でできます。ご興味のある方は、ぜひ下記のコペルプラスのホームページをご覧ください。※『相談支援』をおこなっている教室や事業所は沢山ありますので、お近くの『相談支援事業所』をお探しください。

また、一般社団法人の全国児童発達支援協議会の【加盟施設】がわかるサイトと、コドモブースターという【全国の人気習い事ランキング(療育教室編)】というサイトがありました。こちらのサイトだと、お住いの地域に絞って検索ができます。どんな施設・教室があるのかリサーチするのに使えそうですので、載せておきます。


これ以外に、自費で通うことのできる教室、いわゆる習い事感覚で月謝がかかる所や、個人で活動する専門職に頼ってサポートを受けるという選択肢もあるようです。
療育(発達支援)支援内容
支援内容は、厚生労働省のガイドラインにより基準が決められており、その基準に沿ってそれぞれの施設(教室・事業所含む)が支援を実施しています。
厚生労働省 児童発達支援ガイドライン
児童発達支援ガイドラインを簡単にまとめますと、障害のある子どもや発達が気になるお子さまの発達を促し、自立した生活が送れるように支援する事です。
児童発達支援とは
児童発達支援とは、主に未就学(0~6歳)のお子さまを対象にした、個別や集団療育をおこなう障害福祉サービスの一つです。
お子さまへの発達支援やそのご家族への支援を中心に、日常生活における基本動作や知識技術を習得するためのサポートや、幼稚園などへの入園や小学校への入学に向けた集団生活への適応訓練などの支援をおこないます。
児童発達支援の基本的な役割としては、『発達支援(本人支援や移行支援)』、『家庭支援』、『地域支援』があります。
本人支援
本人支援とは、「お子さまが将来的に、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにすること」を大きな目標とした支援です。「日常生活や社会生活を円滑に営むこと」とはどのようなことを指すのか、具体的に説明します。
①健康・生活 着替えや食事、トイレ、片づけ、持ち物の管理など、日常的におこなう基本の生活動作について、発達段階に応じて習得するためのサポートをおこないます。
②運動・感覚 例えばブロックやボールなど複数の遊具を使った運動など、全身を動かすような大きくてまとまりのある動き(粗大運動)や、机の上での手先を使った工作課題など、細かくて複雑な運動(微細運動)の発達を促すためのサポートをおこないます。
③認知・行動 色や数、大小、長短、高低といった比較に関する基本的な概念、言語理解などといった認知発達を促すためのサポートをおこないます。
指導の中では、指示を聞く、順番を待つ、物の貸し借り、名前を呼ばれたら返事をする、質問には手を挙げるなどのさまざまな場面における適切な行動を経験できるように支援をおこないます。
④言語・コミュニケーション 有意語(意味のある言葉、パパ・ママ・ワンワンなど)や2語文(単語と2つ組わせる、ママとって、ワンワンいたなど)を増やしていくなど、発語や発話を促すサポートや、語彙や簡単な文章、指示の理解を促すサポート、人に対して自分の要求をすること、言いたいことを伝えるための対人でのやり取りを促すサポートをおこないます。
⑤人間関係・社会性 小集団・集団でのゲームやソーシャルスキルトレーニングなどを通じて、ルールを守ることや指示を聞いて行動すること、挨拶や謝罪、返事をするなどの対人関係において基本となる関わり方や接し方を学ぶためのサポートをおこないます。
移行支援
障害の有無に関わらず、全ての子どもが共に成長できるよう、可能な限り、地域の保育・教育などの支援を受けられるようにし、かつ同年代の子どもとの仲間づくりを図る支援です。
家族支援
ご家族が、安心して育児をおこなうことができるよう、さまざまな不安を軽減していくための物理的、また心理的な支援です。
具体的には、指導後のフィードバックや保護者面談、ご家族の方向けのトレーニングを通じて、お子さまの発達状況や支援ニーズの確認、お子さまとの関わり方やコミュニケーションのとり方などに対する相談や助言をおこないます。
地域支援
支援を利用する子どもが地域で適切な支援を受けられるよう、関係機関などと連携を強化していきます。また、地域の子育て支援力を高めるためのネットワークを構築するサポートをおこないます。

放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは、小学生・中学生・高校生の発達が気になるお子さまを対象に、学校の授業終了後や長期休暇中に通うことができ、「自立した日常生活を営むための訓練を受けること」、「地域交流を行うこと」などを目的としたサービスです。
保育所等訪問支援とは
保育所等訪問支援とは、支援の必要なお子様の通う保育所や幼稚園、学校等に、専門知識を持つスタッフが出向き、集団生活に適応するための『直接支援』(お子様への支援)と、『間接支援』(施設や先生への支援)をおこないます。

保育園と幼稚園の違いやメリット・デメリット
◎保育園・・・親が働いている間預かってくれる場所 遅くまで預かってくれるが、協力やフォローが必要なお子様に向いている保育園をみつける事が難しい。ひらがなカタカナ等、学習の時間はお家で作る。
◎幼稚園・・・ざっくり分けて2種類 のびのび系と勉強系がある
☆のびのび系幼稚園のメリットは、遊び時間を多く設定し人間関係、コミュニケーション、集団行動などを身につけていく。お絵描き、工作、室内遊びや外遊びも多い。楽器を使うとしても、カスタネットやトライアングルくらいしか使わず、手先が不器用な子でも達成感が得られる。また、発達障害やグレーゾーンのお子様の受け入れ可能な幼稚園が年々増えています。
☆のびのび系幼稚園のデメリットは、保育園同様ひらがな・カタカナ・数字など、学習の時間が少なく、小学校に入った時に苦労する。勉強時間は、お家で作る。

♢勉強系幼稚園のメリットは、時間割があったり、スムーズな小学校生活を送るために必要な事を幼稚園で教育してくれる。ひらがな・カタカナ・数字・最近は英語の授業もあるようです。色々な楽器を使い、音楽の授業のような時間を過ごしたりします。整列、話しの聞き方、挨拶などもしっかり教育してくれます。もちろん遊ぶ時間もあります。幼稚園にいる間に、スムーズな小学校生活を送るためのスキルが身につきます。幼稚園によって勉強内容・力を入れている場所が違いますのでリサーチが必要です。
♢勉強系幼稚園のデメリットは、言葉の遅れ等発達の遅れが出ている子にはついていけない事が多く、子供を追い詰めすぎたり、自尊心が傷つく恐れがあります。お子様に合っているか慎重な判断が必要かと思います。

近所の保育園・幼稚園のメリットは、呼び出しがあった時にすぐに行ける。見本になるようなお友達と生活することによって、お友達パワーで出来る事が増えるお子様もいます。小学校に入った時に幼稚園のお友達がいて安心できる。デメリットは、お友達やママ友とうまくいかなかった時に、同じ小学校の可能性がある。
保育園・幼稚園の入園をお考えの方は、プレ保育や説明会の参加、お庭開放日などを利用しながら、必ずお子様の症状を園にご相談ください。今は共働きの方も多いでしょうし、時間が取れない方がたくさんいるかと思います。そういう場合は、手っ取り早く、通える範囲の幼稚園を調べて、直接電話して、発達障害・グレーゾーン・発達が気になるお子様の受け入れが可能か、また受け入れた経験・実績があるのかを聞いてしまう手もあります。電話で候補を絞ってから、プレ保育など参加することで時間短縮できます。
また、奇声や多動などで他の園児に危害が及ぶ場合は、入園できたとしても退園を迫られるケースもあります。そういった場合は、お住いの地区町村の窓口に相談し、療育施設などの利用も視野に入れて考えてみてはいかがでしょうか。私はこの3年間が、子供にとってとても大事な期間だと感じています。療育施設を見学し、今のお子様にどのような療育が必要なのかを、福祉のプロの方と一緒に考える事が、今後のお子様のためになってくると思います。
まとめ
療育施設や保育園・幼稚園選びでまず始めにする事は、お住いの市区町村の窓口に相談することです。福祉課や障害福祉課などがありますので、総合案内で相談したい内容を伝えると、適した窓口を教えてもらえます。また、『相談支援事業所』で相談することによって、より多くの情報を集める事ができそうです。お時間があれば2か所くらいは『相談支援事業所』を利用し、比較する事によって偏った情報収集にならないようにしてみてはいかがでしょうか。また、地域の自治体にもよりますが、幼稚園の利用の際、発達障害・グレーゾーンのお子様にフォローの先生が付いてくれる所もあるようですので、市区町村の窓口や幼稚園に確認してみてください。
【通所受給者証】の交付には1ヶ月以上かかる事もあるようですので、【通所受給者証】の取得にも早めにとりかかった方が良さそうです。グレーゾーンのお子様は、【通所受給者証】の取得に時間がかかる場合がありますので、出来るだけ早く取得に向けて動かれた方が良さそうです。施設を利用しなくても、保育所等訪問支援を利用できる事で、行かせたい幼稚園に入園できる可能性が高まると思います。
施設、幼稚園選びは1年前からが理想ですが、少なくとも半年前からは、公的施設や民間施設の体験や説明会、見学会に参加したり、幼稚園もプレ保育があれば利用し、お庭開放日がある所ではどんどん遊びに行き、施設や幼稚園の雰囲気、スタッフや先生の表情や子供との接し方、園児の数に対しての先生の人数、そこを利用しているお子様の様子などを見て、選択肢を絞っていってもいいのではないかと思います。お子様に体験、参加してもらう事によって、お子様が楽しく学べる場所を発見できるかもしれません。毎日、もしくは毎週通う場所なので、駅から近いか、駐車場の有る無しなど、通う事が負担にならないような場所選びも大切だと思います。
※プレ保育とは、幼稚園に入る前に幼稚園で行う事の一部を体験できる保育の事です。幼稚園によっては、このプレ保育に参加していないお子様は、入園が出来ない幼稚園もあります。

また、トレーニングが必要なお子様に対し、世間体があるから幼稚園でいいなど、夫婦やご家族で意見が合わない事もあるかと思います。そういった時もお住いの地区町村や『相談支援事業所』で相談してください。公的な市や区などのサイトでも、そういう相談も受けますと記載されていますので、一人で悩まずに相談してみてください。場合によっては、第三者に間に入ってもらう事で話しがうまく進むこともあります。お住いの地区町村にもよりますが、お子様の一時預かり事業をおこなっている所もありますので、お子様がいるとゆっくり相談できない方はご利用されてはいかがでしょうか。
療育施設の利用は、ご家庭によってバラバラです。お子様の症状によって療育が成功した段階で療育施設から幼稚園に変更する事もできますし、保育園・幼稚園に行きながら療育施設を利用するご家庭もあります。どういう目的で療育施設を利用するかで、利用期間や週に何回通うのかが変わってくると思います。半年だけ療育施設を利用した方も沢山いらっしゃいます。小学生のお子様をもつご家庭によっては、民間の教室や事業所で、運動に特化した施設を1箇所、放課後等デイサービスのみ提供している施設(学習支援と預かり型)を2箇所の計3箇所を利用している方もいるようです。
複数箇所の利用が可能なようですので、お子様に合わせた組み合わせが出来るようです。色々な利用方法がありますので、とにかく相談する事が一番だと思います。
相談や体験、説明会に行かれる際は聞き忘れがないように、聞きたい事・確認したい事を、メモしてからのご参加をおすすめいたします。

一番大切な事は、お子様が怒られながら、叱られながら学ぶのではなく、お子様の特性を理解して楽しく学んでいける事が本当に大切だと思います。気持ちをうまく説明できないお子様もいますので、お子様に寄り添い、ご家庭に合った療育施設や保育園・幼稚園が見つかる事を願っています。

学習面で取り入れたい事
学習面では、お家での学習が必要になってくると思います。小学校に上がる前に、ひらがな・カタカナ・数字の読み書きができないと、国語の授業でつまずきます。小学校からは漢字を覚えないといけないので、我が子イルカくんのように、書けないまま小学校に上がると、本当に苦労させてしまいます。育てる事に必死で小学校を視野に入れた考えを何も持っていなかったことを、とても反省しています。ですので、小学校に上がるまでにひらがな・カタカナ・数字が書けるようになっているのが理想的かと思います。お子様の症状にもよりますので、お子様に無理のない範囲で、楽しく学ばせてあげてください。
イルカくんは、3年生でやっと漢字が追い付き、漢検の8級(3年生漢字)、7級(4年生漢字)合格しています。ADHDのお子様には、その子に合った勉強方法を見つけてあげる事が大事だと思います。
①お金をかけずに楽しく学ぶ方法を試してみる。100均のひらがなドリルなどを使ってなぞる。私の経験上、書いて覚えるのが一番早く覚えてくれます。なぞらせて覚えてもらう事が近道かと思います。もしくは、携帯でひらがな練習のアプリをダウンロードして練習してもらう。指でなぞらせるより、タッチペンを使わせた方が字もうまくなるし、ゲーム感覚で夢中でやってくれたりします。iPadがあると、さらに食いつきが良かったりします。また、イルカくんのように聴覚優位のお子様には耳から入る情報の方が覚えやすいので、声を出しながら書く事で覚えが早くなったりします。私のブログの『こどもの発達障害の検査や診断まで流れ』の中で、聴覚優位・視覚優位について書いてあります。
イルカくんはADHDがあるので、字を覚える事が苦手です。またすぐに忘れてしまうので、同じ字を毎日毎日繰り返し書く事が大事でした。字を続けて書く事を嫌うので、例えばア、イ、ウの3個くらいの字を毎日毎日1週間とか2週間くらい、一文字二文字くらいを繰り返し書いてもらう。1日1分もあれば終わってしまくらいの量です。どんどん先に進まない事が大事でした。これを繰り返すことで、3文字続けて書けるようになったり、覚える字を増やしていったり、学ぶ時間を少しずつ増やしていけます。これは漢字でも変わりません。スッと覚えてしまう字と何回書いても覚えられない字があるので、時間をかけて覚える字と、定期的に覚えてるか確認するくらいで大丈夫な字があったりします。
現在も、イルカくんはノートに1列ずつ漢字を書かなければいけない宿題を、5文字ずつくらいしか書きません。下手すると3文字の日とかあります。それ以上の事をさせようとすると宿題自体をやらなくなってしまうので、完璧を求めすぎない事も大事です。
本当に効果あるので、字を覚えるのが苦手なお子様には、ぜひやってみてください。楽しく、そして褒めて伸ばす。字が汚くて読めなくても今はOK!時間はかかりますが、4年生くらいから読める字になります(≧▽≦)四角い枠の中に書く事を嫌う子もいますので、その場合は自由帳や大きいマスの漢字ノートなどから始めても良いと思います。
②アンパンマンよみかきタブレットなどのおもちゃを買って、遊びの中で学ばせる。下の子はこれでひらがな・カタカナを覚えました。
③プロに任せる。発達障害、グレーゾーン、学習障害のお子様向けの塾や、通信教材で楽しく学んでもらう。天神という通信教材は、放課後等デイサービスや支援学級でも取り入れている所もあるほどの教材です。発達障害、学習障害の子にも向いている学習方法を取り入れています。小学校で、勉強についていけなくなっている子にも使え、さかのぼって勉強できたりもします。こんな所もあるんだなと知っておくだけでも、選択の幅が広がるかと思いますので、いくつか載せておきます。申し込みをお考えの方は、まずは何社か資料請求してみてください。内容や金額などを比べたり、資料請求することによって無料体験が出来たりもします。利用できるものは利用して、お子様の反応を見てください。